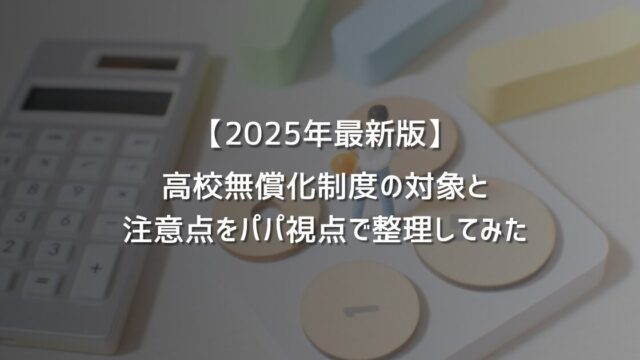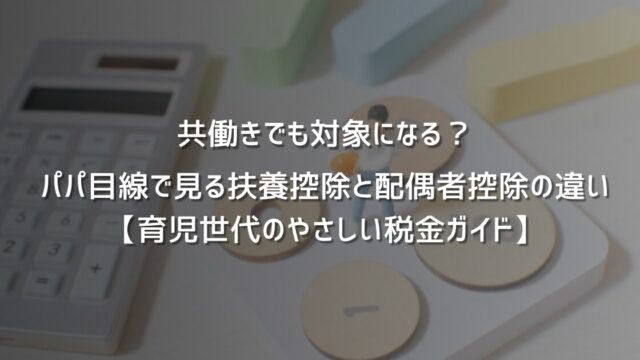「そろそろ2人目、3人目を考えたいな…」
お子さんとの生活に慣れ、そんな風に考えるパパも多いでしょう。
しかし、家族が増える喜びと同時に、現実的なお金の悩みも出てきます。
特に、毎月の家計に重くのしかかる「保育料」。
僕自身一人の子どもを育てるだけでも将来かかってくる費用を考えると色々と考えてしまいます…
調べてみると、日本には2人目、3人目の子どもがいる家庭(多子世帯)を支援するための、保育料の「きょうだい割引」や様々な「保育料軽減制度」がちゃんと用意されているようです。
これらの制度を正しく理解し、忘れずに活用することで、保育料の負担は想像以上に軽くなるかもしれません。安心して新しい家族を迎える準備を、今日から進めることができるのです。
この記事では、そんな子育て世代のパパさんたちに向けて、
- 2人目・3人目の保育料が本当に安くなる仕組み
- 国の「きょうだい割引」と自治体独自の支援策
- 知っておくべき注意点と、パパがやるべきこと
などを、パパ目線で、分かりやすく徹底解説していきます。

結論:2人目・3人目の保育料は安くなる可能性大!
まず、多くのパパが最も知りたいであろう結論からお伝えします。
答えは「イエス」です。
多くの場合、特に兄弟姉妹が同時に保育施設を利用している場合、保育料の負担は国の制度や自治体の取り組みによって確実に軽減されます。
その背景には、「少子化」という課題に対し、多子世帯の経済的負担を社会全体で軽くし、安心して子どもを産み育てられる社会を目指す、という国の明確な方針があるのです。
保育料軽減の基本:「幼児教育・保育の無償化」とは
具体的な「きょうだい割引」の話の前に、現在の保育料制度の大前提である「幼児教育・保育の無償化」について、簡単におさらいしておきましょう。この制度を理解しているかで、今後の話の理解度が大きく変わります。
「無償化」の対象年齢と施設
原則として、満3歳になった後の4月1日から小学校に入学するまでの3年間(いわゆる3歳~5歳児クラス)の子どもたちの保育料が無償化の対象です。
対象となる施設は、認可保育所、幼稚園(月額2.57万円まで)、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業などが主です。
【注意】すべてが無料になるわけではない!
「無償化」という言葉から、「保育園にかかる費用が全て無料になる」と誤解しがちですが、そうではありません。
無償化の対象は、あくまで毎月の基本的な保育料(利用料)のみです。
以下の費用などは、これまで通り保護者の実費負担となる場合が多いので注意しましょう。
- 給食費(特に3歳以上児クラスのおかず代やおやつ代など)
- 通園送迎バスの利用料金
- 制服代、教材費、PTA会費、行事費など

2人目・3人目の保育料はどう安くなる?国の多子軽減制度
では、3歳未満の0歳~2歳児クラスの保育料や、無償化の対象外となる費用はどうなるのでしょうか。ここからが「きょうだい割引(多子軽減)」の本題です。
0歳~2歳児クラス:第2子は半額、第3子以降は無償に!
住民税が課税されている一般的なご家庭の場合、国の基本的な制度として、0歳~2歳児クラスの保育料は以下のように軽減されます。
- 第2子:保育料が半額
- 第3子以降:保育料が無償(無料)
(※ちなみに、住民税非課税世帯の場合は、さらに手厚く、第1子から保育料が無償となります。)
【超重要】「きょうだい」のカウント方法と所得制限の撤廃
この素晴らしい制度を理解する上で、最も重要なのが「きょうだい」のカウント方法です。
- 国の基本的なルール:
小学校就学前の範囲にいる子どもが、保育所などの対象施設を同時に利用している場合に適用されます。上の子から順に第1子、第2子…とカウントします。
つまり、一番上のお子さんが小学校に入学すると、原則としてこのカウントからは外れてしまいます。その場合、それまで「第2子」として半額だった真ん中のお子さんが「第1子」扱いとなり、保育料が満額に戻ってしまう可能性があるのです。これはパパとして絶対に知っておくべき重要なポイントです。 - 【朗報】所得制限の撤廃へ!
以前は、この軽減措置に「世帯年収おおよそ360万円未満」という所得制限がありました。しかし、子育て支援策の拡充により、この所得制限は令和7年度(2025年度)から完全に撤廃される予定です。(※2025年6月現在。お住まいの自治体では既に撤廃されている場合もあります)
これにより、これまで対象外だった多くの家庭も、この大きな恩恵を受けられるようになります。
【要チェック】お住まいの自治体はもっとお得かも?
国の基本的な制度に加えて、多くの市区町村では、さらに手厚い独自の保育料軽減制度を設けています。パパ自身が情報収集のアンテナを高く張ることが、家計を助ける鍵となります。
自治体独自の「神レベル」支援策の例
- 第2子からの保育料完全無償化:国の制度よりも手厚く、所得に関係なく第2子から保育料が無料になる自治体も存在します。
- きょうだいの年齢制限の緩和:国の基準では対象外となる小学生以上の兄姉まで「きょうだい」としてカウントし、下の子の保育料を軽減してくれる自治体もあります。
- 独自の給付金制度:「第〇子誕生お祝い金」や「多子世帯応援給付金」など、一時的な助成金を支給している場合もあります。
パパが今すぐできる情報収集アクション
- 自治体の公式ウェブサイトを徹底検索!
「(お住まいの市区町村名) 保育料 軽減 きょうだい」「(市区町村名) 多子世帯 支援」といったキーワードで検索してみましょう。 - 分からなければ役所の窓口へ!
ウェブサイトで情報が見つからない、あるいは自分の家庭のケースでどうなるか知りたい場合は、迷わず市区町村の保育担当課や子育て支援課に電話で問い合わせてみましょう。

パパが知るべき注意点と申請のポイント
これらのありがたい保育料軽減制度ですが、残念ながらいくつかの注意点や「落とし穴」も存在します。事前に理解し、後悔のないようにしましょう。
注意点1:認可外保育施設などを利用する場合
認可外保育施設や企業主導型保育事業を利用する場合も、国の無償化や多子軽減の対象となる場合がありますが、認可保育所とは条件や上限額が異なることがあります。また、施設独自の「きょうだい割引」制度が設けられていることも多いため、必ず利用を検討している施設に直接確認することが重要です。
注意点2:保育料以外の費用は別途かかる
保育料そのものが無償や半額になっても、前述の通り、給食費や延長保育料、行事費などは別途必要です。「保育園にかかるお金がゼロになる」と楽観視せず、これらの「保育料以外の費用」もきちんと予算に組み込んでおきましょう。
注意点3:【最重要】軽減制度は「申請」しないと適用されない!
これが最も重要な注意点です。これらの素晴らしい制度は、多くの場合、ただ待っているだけでは適用されません。原則として、保護者からの「申請」が必要です。
入園申し込み時や毎年度の更新手続きの際に、役所や保育施設から必要書類の提出を求められます。これらの手続きを忘れたり、期限に遅れたりすると、せっかくの軽減措置を受けられなくなってしまうという悲劇も起こり得ます。
パパのアクションプラン:今日からできる4ステップ
保育料軽減制度を賢く活用するために、パパが今すぐやるべきことを4つのステップにまとめました。
- 【情報収集】まずはお住まいの自治体の制度を徹底確認!
ウェブサイトや役所の窓口を活用し、我が家が使える制度は何かを正確に把握しましょう。 - 【夫婦で共有】パパが集めた情報をママと共有し、家族の状況と照らし合わせる!
家計の状況や働き方、家族の夢などを総合的に考慮し、どの施設をどのように利用するのが最適か、夫婦でとことん話し合いましょう。 - 【申請手続き】必要書類の準備と提出期限の厳守をパパが率先して行う!
手続きをママ任せにせず、夫婦でダブルチェックし、申請漏れや不備がないように完璧にこなしましょう。 - 【継続的な見直し】ライフプランの変化に合わせて、適用制度や条件を定期的に確認する!
子供の成長や家族の状況の変化に合わせて、常に最新の情報をキャッチアップし、その時々で最適な支援を受けられるようにしましょう。

まとめ:保育料不安を解消し、笑顔で家族計画を進めよう
2人目、3人目の子どもが増えることは、決して経済的な負担が増えることだけを意味しません。
適切な手続きを行えば、国の制度や自治体の支援によって、保育料の負担は想像以上に軽減される可能性があります。
特に、0歳~2歳児クラスの保育料は、国の制度により第2子は半額、第3子以降は無償になります。これに自治体独自の支援が加われば、さらに大きな助けとなるでしょう。
しかし、これらの恩恵を受けるためには、パパ自身が主体的に情報収集し、ママと協力して、必要な申請手続きを確実に行うことが不可欠です。
お金の不安を知識で解消し、安心して新しい家族を迎える計画を立てること。これもまた、パパの大切な役割です。
まずはあなたのお住まいの市区町村のウェブサイトで、「保育料 きょうだい 軽減」と検索して情報収集してみましょう!
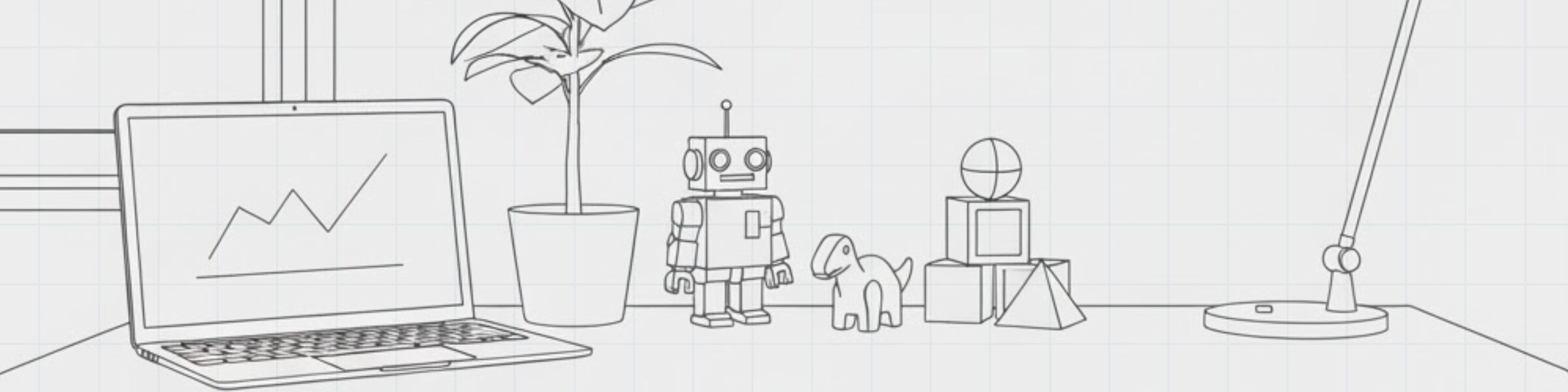

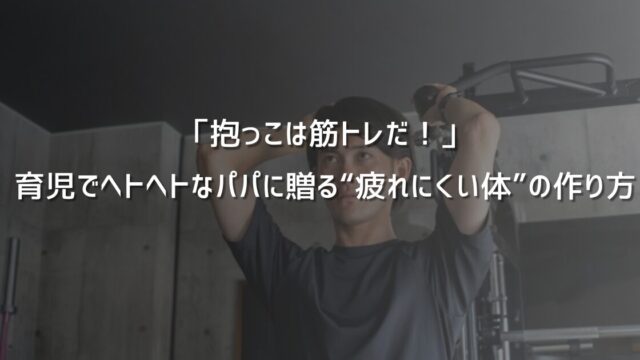



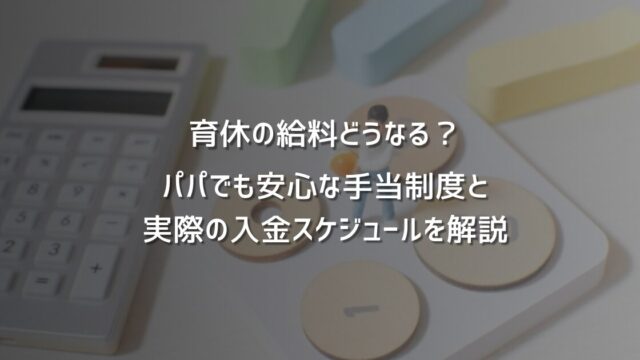


.jpg)