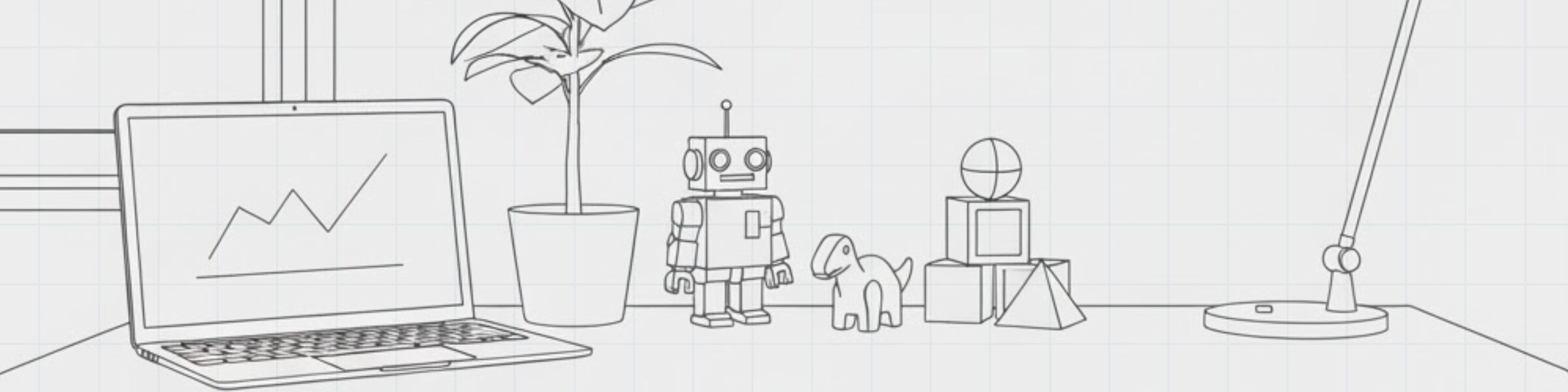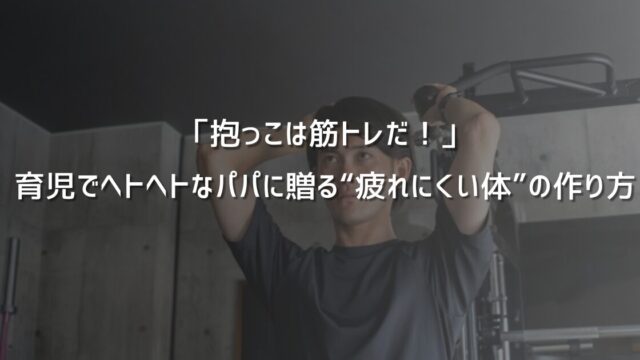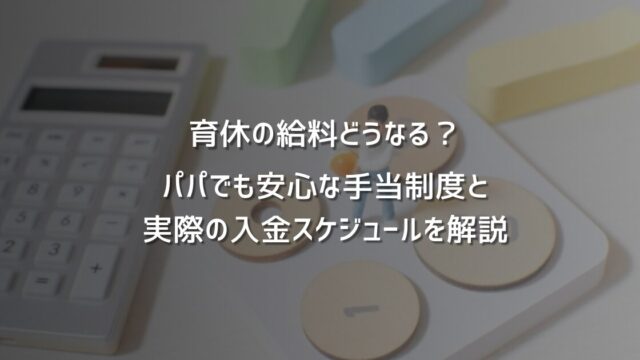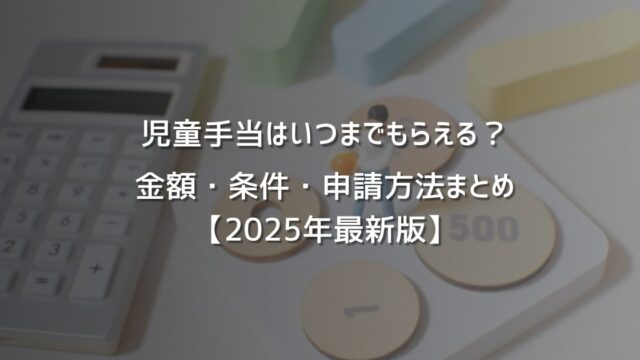こんにちは、30代で2歳の男の子のパパ、ブロガーの「ケンタ」です。
我が家は妻もフルタイムで働く共働き家庭。息子の将来を考えると、一番に頭をよぎるのが「教育資金」のこと。特に息子は重度の喘息持ちということもあり、将来の選択肢を狭めないためにも、お金の準備はしっかりしておきたいと夫婦でよく話し合っています。
子どもの教育資金準備は、パパママにとって最重要ミッションの一つ。そんな時、多くの人がまず検討するのが「学資保険」ではないでしょうか。「子供が生まれたら学資保険」というのが、一昔前の“常識”だったかもしれません。
しかし、本当に「学資保険ありき」で大丈夫なのでしょうか?
実は、我が家では夫婦で徹底的に話し合い、様々な情報を比較検討した結果、「学資保険は契約しない」という結論に至りました。もちろん、学資保険が悪いわけではありません。それぞれの家庭の状況や考え方によっては、最適な選択肢となる場合もあります。
この記事では、
- 学資保険のメリット・デメリット
- 我が家が「学資保険不要」と判断したリアルな理由
- 学資保険なしで、具体的にどう教育資金を準備しているか(我が家の実践方法)
- それでも学資保険が向いているかもしれない家庭とは?
といった内容を、2025年現在の最新情報(特に新NISA制度などを踏まえ)で、同じ子育て世代のパパとして、分かりやすくリアルにお伝えします。この記事が、あなたの家庭にとってベストな教育資金準備方法を見つけるための一助となれば幸いです。

学資保険の基本:メリット・デメリットを徹底比較
まずは、「学資保険」がどのような金融商品なのか、その基本的な仕組みと、メリット・デメリットを冷静に整理してみましょう。
学資保険の仕組みと主な特徴
学資保険とは、子どもの教育資金を準備することを主な目的とした貯蓄型の保険です。毎月または毎年、一定の保険料を払い込み、子どもの進学時期に合わせて「お祝い金」や「満期保険金」としてまとまったお金を受け取れるのが一般的です。
主な特徴は以下の通りです。
- 貯蓄性: 教育資金を着実に積み立てる機能。
- 保障性: 親(契約者)に万が一のことがあった場合、以降の保険料の払込みが免除される「保険料払込免除特約」が付いていることが多い。
- 受取タイミング: 高校入学時、大学入学時など、まとまった資金が必要な時期に合わせて受け取れるように設計されています。
学資保険のメリット・デメリット一覧
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ①強制的に貯蓄できる 貯金が苦手でも計画的に貯められる。 | ①返戻率が低い 元本割れのリスクがあり、増えにくい。 |
| ②親の万が一に備えられる 払込免除特約で教育資金を確保できる。 | ②インフレに弱い 物価が上がると、お金の価値が目減りする。 |
| ③生命保険料控除の対象になる 所得税・住民税が少し安くなる可能性がある。 | ③途中解約で損をする 解約すると元本割れする可能性が高い。 |
| ④柔軟性に欠ける 運用先を選んだり、引き出したりしにくい。 |
我が家が学資保険を選ばなかった3つの理由
上記のメリット・デメリットを踏まえ、我が家では「学資保険は不要」という結論に至りました。その主な理由と、そこに至るまでの葛藤についてお話しします。
理由1:低すぎる返戻率とインフレへの懸念
まず一番大きかったのが、返戻率の低さです。いくつかの学資保険を比較しましたが、魅力的な商品はなかなか見つかりませんでした。むしろ元本割れする商品もあり、「これなら銀行預金と大差ないのでは?」と感じました。
さらに、10年以上の長期契約になるため、将来物価が上昇するインフレリスクを無視できないと考えました。
理由2:より柔軟で期待リターンの高い「新NISA」の存在
低金利時代において、貯蓄だけで教育資金を準備するのは非効率だと感じ、ある程度のリスクは許容しつつ、より高いリターンが期待できる資産運用に目を向けました。
特に、2024年から始まった「新NISA」制度は、非課税で投資できる金額や期間が大幅に拡大され、教育資金のような長期的な資産形成との相性が抜群だと感じたのです。
理由3:万が一の保障は「収入保障保険」で合理的にカバー
学資保険の大きなメリットである「保険料払込免除特約」。これは確かに魅力的です。しかし、契約者である私(パパ)に万が一のことがあった場合の保障は、掛け捨ての「収入保障保険」で備える方が合理的だと判断しました。
収入保障保険は、比較的安い保険料で、遺された家族の生活費を長期間にわたって保障してくれるため、教育資金だけでなく、生活全般をカバーできると考えたからです。

学資保険以外の選択肢:我が家の教育資金準備プラン
では、具体的に我が家がどのように教育資金を準備しているのか、そのリアルな計画と実践方法をご紹介します。これはあくまで一例として、ご家庭の状況に合わせてアレンジしてください。
基本方針:目標額の設定と長期積立計画
まず、子どもの進学コースを想定し、教育資金の目標額を設定しました。文部科学省のデータなどを参考に、子ども一人あたり約1,500万円~2,000万円を目安にしています。そして、子どもが0歳の時から大学入学までの約18年間で、これをどうやって積み立てるか、長期的な計画を立てました。
実践方法1:【新NISA】をフル活用した夫婦での非課税投資
我が家の教育資金準備の主軸は、何と言っても「新NISA」です。
- つみたて投資枠: 毎月、夫婦それぞれで一定額を、全世界株式や米国株式などのインデックスファンドにコツコツと積み立てています。「長期・積立・分散投資」を基本とし、リスクを抑えながら着実な資産形成を目指します。
- なぜNISAか?: 最大のメリットは運用益が非課税になることです。そして、いつでも引き出しが可能なので、学資保険のように途中解約で元本割れする心配が少ない(※投資なので元本保証はありません)という柔軟性も魅力です。
実践方法2:児童手当は手をつけず専用口座で積立・一部運用
国から支給される児童手当は、原則として手をつけずに、子どもの教育資金専用口座に全額貯蓄しています。そして、ある程度まとまったら、一部を新NISAの資金に充てるなど、ここでも運用を意識しています。「最初からなかったもの」として扱うのがポイントです。
実践方法3:毎月の「先取り貯蓄」で着実に資金を積み上げる
毎月の給料日に、一定額を自動的に教育資金用の口座に振り替える「先取り貯蓄」を徹底しています。また、夫婦それぞれのボーナスからも、無理のない範囲で一部を教育資金に充当しています。
それでも学資保険が「向いている」家庭とは?
ここまで我が家が「学資保険不要」と判断した理由や代替案をお伝えしてきましたが、学資保険が最適な選択となるご家庭ももちろんあります。
- どうしても計画的な貯蓄が苦手で、強制力が必要だと感じる家庭
- 投資のリスクは一切取りたくない、元本保証に近い形を強く望む家庭
- 契約者に万が一のことがあった場合の「払込免除」を最重視する家庭
これらのニーズに合致する場合は、学資保険も有力な選択肢となるでしょう。

まとめ:教育資金準備に絶対の正解はない。夫婦で話し合い、我が家に合った方法を見つけよう
子どもの教育資金準備に、「これさえやっておけば絶対に大丈夫!」という万能な方法はありません。学資保険も、あくまで数ある選択肢の一つです。
大切なのは、学資保険のメリット・デメリットを正しく理解した上で、ご自身の家庭の状況、将来設計、リスク許容度、そして何よりも夫婦の価値観に照らし合わせて、「我が家にとって本当に必要なのか?」を徹底的に話し合い、判断することです。
我が家の事例は、あくまで「こんな考え方もあるんだな」という一つの参考として捉えていただければ幸いです。
重要なのは、情報を鵜呑みにせず、ご自身で調べ、考え、そして何よりも夫婦でしっかりとコミュニケーションを取り、納得のいく結論を出すことです。子どもたちの輝かしい未来のために、今日からできる一歩を、一緒に踏み出していきましょう!
https://dad-note.com/koukou-mushouka-2025-papa