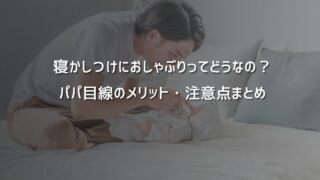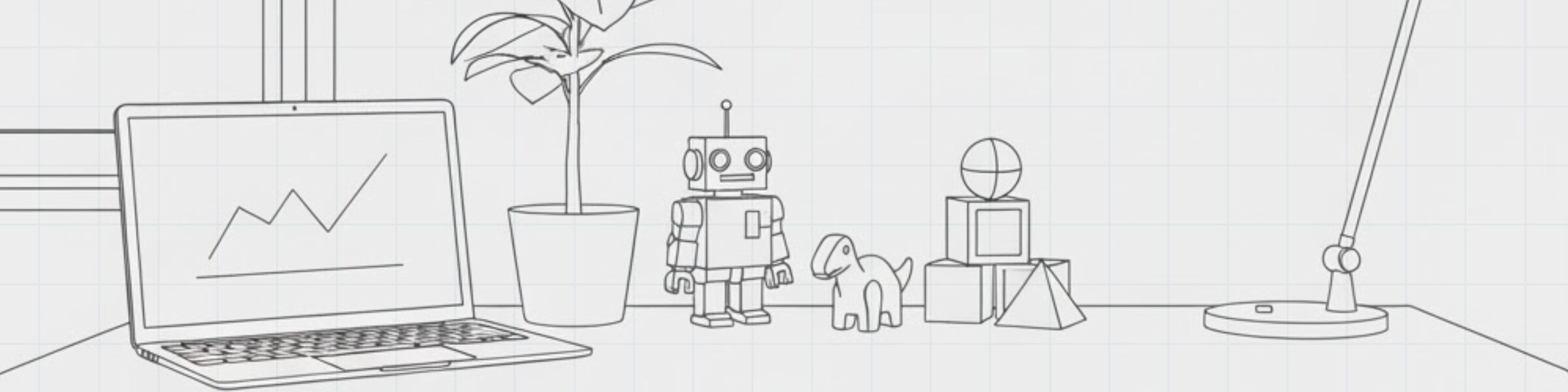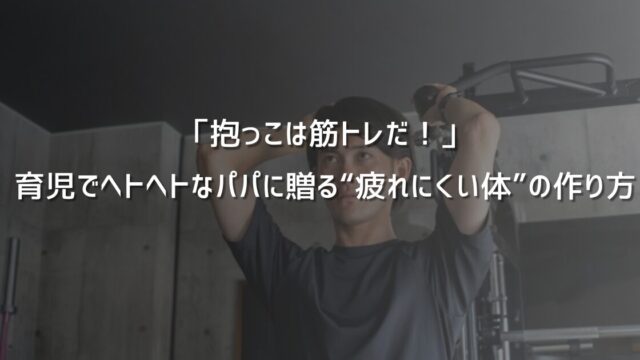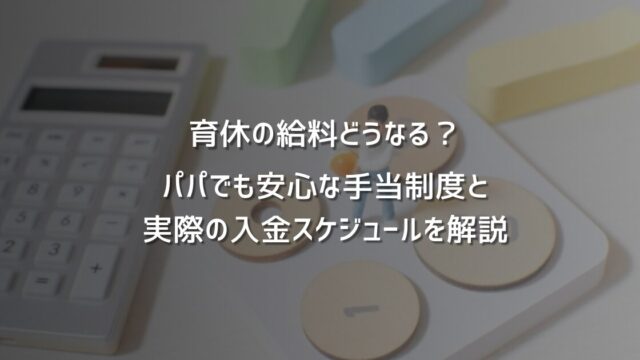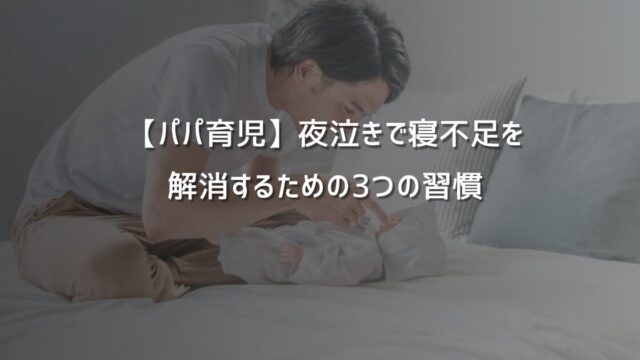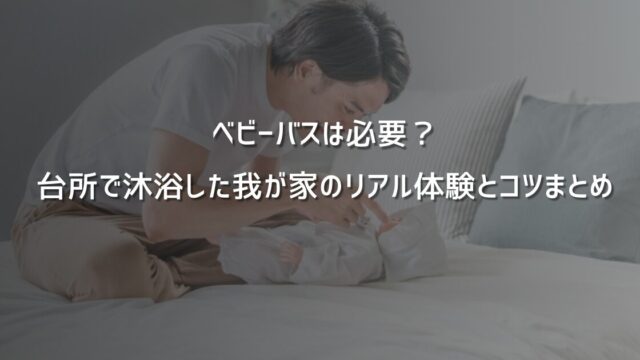こんにちは、30代で2歳の男の子のパパ、「ケンタ」です。
我が家は妻もフルタイムで働く共働き家庭。息子との毎日は、かけがえのない喜びで満ちていますが、正直寝かしつけに関しては、まさに「地獄」と表現したくなるような壮絶な日々でした。
特に息子は重度の喘息持ちで、寝入りばなに咳き込んでしまい、なかなかスムーズな入眠が叶わないこともしばしば…。
この記事を読んでくださっている20代~40代の、特に初めての育児に奮闘中のパパさんたちの中にも、
「抱っこじゃないと絶対に寝ない…もう腕が限界を超えている…」
「どこにそんな元気を隠していたんだ…夜寝る準備をしてから最高潮のテンションに突入!」
出口の見えない寝かしつけとの壮絶な戦いに、心身ともに疲れ果て、消耗しきっている方がいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は私と同様の悩みを抱え、試行錯誤を繰り返しているみなさんと一緒に穏やかな睡眠を勝ち取るために「寝かしつけっていつまで続くのか」について調べました。
- 「寝かしつけ」って、そもそもいつまで必要なの?そして避けられない「個人差」という現実
- 【我が家のリアル体験談】2歳喘息っ子の寝かしつけ卒業へ!試行錯誤の全7ステップ!
- ステップ1:全ての基本はここから!「ねんね環境」の徹底的な見直しと最適化プロジェクト
- ステップ2:毎日同じ時間に、同じ流れで!パパも積極的に参加する
- ステップ3:夜の安眠は昼間の活動量で決まる!太陽をたっぷり浴びて、思いっきり遊んで、心地よい疲れを戦略的に誘う「日中の過ごし方改革」
- ステップ4:【パパと挑戦】焦らない、比べない「セルフねんね」を促す、ゆるやかな距離の置き方
- ステップ5:心の拠り所をそっと用意!お気に入りの「安心グッズ(トランジション・オブジェクト)」の魔法の力を借りる
- ステップ6:言葉の持つ偉大な魔法!自信と安心感を優しく、そして具体的に伝える
- ステップ7:何よりも、そして誰よりも大切!焦らず、比べず、根気強く!
- 寝かしつけ卒業にむけて。パパが積極的にできること・常に心がけておきたい大切なこと
- もし、どうしても寝かしつけが辛く、親子関係や夫婦関係にまで悪影響が出始めているなら…専門家への相談もためらわないでください
- まとめ:寝かしつけ卒業は、揺るぎない成長の証!焦らず、比べず、深い愛情を持って、夫婦で楽しみに待とう!
「寝かしつけ」って、そもそもいつまで必要なの?そして避けられない「個人差」という現実
まず、多くのパパママが知りたい「この寝かしつけって、一体いつまで続くの?」という疑問について。
一般的な専門家の意見や育児書の情報を参考にしつつ、どうしても避けられない「個人差」という現実について、しっかりと理解を深めておきましょう。
乳児期(0歳~1歳未満):まだまだ手厚い愛情とスキンシップによる寝かしつけが不可欠な時期
生まれたばかりの赤ちゃんは、昼と夜の区別もまだ曖昧で、睡眠サイクルも非常に未熟です。
ママのお腹の中にいた時のような絶対的な安心感を求め、抱っこや授乳、優しいトントンなどで眠りにつくのがごく一般的。
この時期は、赤ちゃんの求めるままに、たっぷりの愛情とスキンシップで安心感を与え、手厚い寝かしつけをしてあげるのが基本中の基本です。パパの出番もたくさんありますよ!
我が家の場合はミルクを上げるとそのまますんなり寝ることが多かったのですが、そのためにミルクを過剰に上げてしまうことが多かったです…笑
幼児期前半(1歳~3歳):少しずつ「一人で眠る力」を育む大切な準備期間。ねんねルーティンが鍵!
1歳を過ぎると昼間の活動時間も格段に増えてきます。
少しずつですが、生活リズムも整い始め、毎日同じ時間に同じことを繰り返す「ねんねルーティン(入眠儀式)」を取り入れることで、スムーズな入眠を促せるようになってくる子も増えてきます。
寝かしつけの方法も、終始抱っこから、添い寝でのトントンや絵本の読み聞かせへと移行していく時期です。
ちなみに、2歳になる我が家の息子は、寝る前に必ず耳掃除をしてから体のマッサージをするようにしています。
部屋を暗くしてからは、しばらくおしりや背中をトントンするといった寝かしつけがまだ必要ですが、以前に比べると格段に寝つくまでの時間が短縮され、時には一人でゴロゴロしているうちに眠ってしまうことも出てきました。
幼児期後半(4歳~就学前):多くの子が「セルフねんね」の入り口に立つが…油断は禁物、個人差は依然として大きい!
一般的に、4歳~5歳頃になると、多くの子が大人に頼らず、自分一人で布団に入って眠れるようになると言われています。いわゆる「セルフねんね」の達成です。しかし、これはあくまで一般的な目安であり、子供の性格や発達のペース、家庭環境の変化によって、まだまだ手厚い寝かしつけが必要な子も少なくありません。焦りは禁物です。
一人で寝れるようにようになると、両親も自分の時間をとりやすくなりますよね。嬉しいような寂しいような。
「寝かしつけ、いつまで?」その問いに絶対的な正解はない!焦らず、比べず、我が子の個性とペースに寄り添うことが大切
結局のところ、「寝かしつけがいつまで必要か」という問いに対して、全ての子に共通する絶対的な正解は存在しません。
最も大切なのは、SNSなどで見かける他の子の状況と比べることなく、焦らず、我が子の唯一無二の個性と、その子なりの発達のペースに、親としてどっしりと寄り添い、その時々で最適なサポートと愛情を注いであげることだと、僕は強く信じています。

【我が家のリアル体験談】2歳喘息っ子の寝かしつけ卒業へ!試行錯誤の全7ステップ!
「一般的な目安や心構えは分かったけど、じゃあ具体的に、どんなことから始めたらいいの?」という、実践派のパパさん、大変お待たせいたしました!
ここからは、我が家が喘息持ちで寝つきの悪かった2歳の息子を相手に日々試行錯誤を繰り返してたどり着いた現状の対策を7ステップに分けて解説します。
まだまだ先輩パパたちには届いていないかもしれませんがなにか参考になれば幸いです。
ステップ1:全ての基本はここから!「ねんね環境」の徹底的な見直しと最適化プロジェクト
赤ちゃんが安心して、そして心地よく眠りにつくためには、快適な睡眠環境を整えることが不可欠です。これは寝かしつけの土台作りであり、最も基本的なステップと言えるでしょう。
- 部屋の明るさを調整する。
- 温度・湿度の徹底管理
- 寝具の快適性チェック
まずは部屋の明るさを見直しました。明るい部屋から急に暗い寝室に連れて行っても赤ちゃんはびっくりして興奮状態になります。寝る1時間前にはリビングの明るさを落として暗さに慣らしていくようにしています。
また、我が子は喘息持ちなので、寝室の湿度の管理の為に空気清浄機能付きの加湿器を導入。寝具そのものも寝やすく、モケモケが出にくいものを選びました。
ステップ2:毎日同じ時間に、同じ流れで!パパも積極的に参加する
毎日寝る前に、できるだけ同じ時間に、同じ流れで、同じことを繰り返す「入眠儀式(ねんねルーティン)」は、赤ちゃんに「あ、もうすぐ寝る時間なんだな」という心の準備をさせ、スムーズな入眠へと誘うための、非常に効果的で重要な習慣です。
我が家では、毎日晩ご飯のあとはお薬タイム。お薬のあとにお風呂に入って。マッサージ。すると、自然とうとうとしだします。
またベットでの寝かしつけはパパの担当です。
赤ちゃんの頃から僕がずっと寝かしつけ担当なので、眠たくなってくると僕に抱っこおねだりしてくるので、息子の中でも夜のおねんねはパパの仕事とわかっているみたいですね。
ステップ3:夜の安眠は昼間の活動量で決まる!太陽をたっぷり浴びて、思いっきり遊んで、心地よい疲れを戦略的に誘う「日中の過ごし方改革」
夜にぐっすりと、そしてスムーズに眠りについてもらうためには、実は日中の過ごし方が非常に重要な鍵を握っています。
- 午前中に太陽の光を全身でたっぷり浴びる
- 日中は年齢と体力に合わせて思いっきり体を動かして遊ぶ!
日中にしっかりと体を使って遊ぶと夜も自然と寝るようになりました。
ステップ4:【パパと挑戦】焦らない、比べない「セルフねんね」を促す、ゆるやかな距離の置き方
快適な睡眠環境と一貫したねんねルーティンが確立されてきたら、次のステップは、お子さんの「一人で眠る力(=セルフねんね)」を、愛情を持って育んでいくための具体的なアプローチです。
いわゆる「ねんねトレーニング(ねんトレ)」と呼ばれるものには様々な方法がありますが、我が家ではあまりストイックになりすぎず、息子の性格やその日の様子を見ながら、少しずつ、そして柔軟に進めていきましょう。
ステップ5:心の拠り所をそっと用意!お気に入りの「安心グッズ(トランジション・オブジェクト)」の魔法の力を借りる
常にそばにいなくても、赤ちゃんや小さなお子さんが安心して眠りにつけるように、お気に入りのぬいぐるみや、肌触りの良いタオル、特定のブランケットなどを「安心グッズ(専門的にはトランジション・オブジェクトと言います)」として与えるのも、非常に有効な方法の一つと言われています。
我が子はIKEAで買ったサメのぬいぐるみがお気に入りで最近は寝るときは両手に抱えてベッドに向かうことも。
ステップ6:言葉の持つ偉大な魔法!自信と安心感を優しく、そして具体的に伝える
子供の言葉の理解力は、大人が想像している以上に、日々目覚ましく発達しています。
一人で寝るのは怖いことじゃないよとコミュニケーションをしっかりと取って一人ねんねへ挑戦中です。
ステップ7:何よりも、そして誰よりも大切!焦らず、比べず、根気強く!
寝かしつけ卒業への道は、決して平坦な一本道ではありません。
むしろ、険しい山あり谷あり、時には後退もしながら進む、長い道のりです。お子さんの体調が悪かったり、日中何か嫌なことや怖いことがあったり、あるいは環境が少し変わったりするだけで、一時的に赤ちゃん返りのように寝かしつけが困難になり、以前よりも手がかかるようになることも日常茶飯事です。
寝かしつけ卒業にむけて。パパが積極的にできること・常に心がけておきたい大切なこと
寝かしつけは、決してママ一人だけにその重責を負わせるべきものではありません。
「寝かしつけは、なんとなくママの仕事なんでしょ?」という、昭和の化石のような古い考えは、今すぐ、この瞬間に、きっぱりと捨て去りましょう。
パパも積極的に寝かしつけに参加し、時にはママと役割を分担したり、ママが疲れ果てている時や体調が悪い時には率先して寝かしつけの全責任を担当したりすることで、ママは心身ともに救われ、感謝の気持ちでいっぱいになるはずです。
もし、どうしても寝かしつけが辛く、親子関係や夫婦関係にまで悪影響が出始めているなら…専門家への相談もためらわないでください
寝かしつけが全くうまくいかず、親子ともに心身ともに疲れ果て、笑顔が消え、日常生活に支障が出始めている…
そんな限界的な状況に陥ってしまったら、決して一人で、あるいは夫婦だけで抱え込まず、勇気を出して専門家の力を借りることも真剣に考えてみてください。
- 頼れる相談先の例:
- かかりつけの小児科医
- お住まいの地域の保健センターの保健師さん
- 子育て支援センターの経験豊富な相談員さん
- 場合によっては、子供の睡眠を専門とする医師や、夜泣き・寝かしつけ専門のコンサルタントなど
ごく稀なケースではありますが、背景に睡眠障害といった医学的な問題が隠れている可能性もゼロではありません。
専門家からの的確なアドバイスやサポートを受けることで、思わぬ解決の糸口が見つかるかもしれません。

まとめ:寝かしつけ卒業は、揺るぎない成長の証!焦らず、比べず、深い愛情を持って、夫婦で楽しみに待とう!
寝かしつけの時間は、確かに大変なことも、辛いことも、数えきれないほど多いかもしれません。しかし、お子さんの寝顔を間近で見つめ、柔らかな温もりを感じ、無防備な寝息に耳を澄ませられる、かけがえのない二度と戻らない貴重な時間です。
一瞬一瞬を大切に、いつか訪れる「寝かしつけ卒業の日」を、深い愛情を持って、夫婦で手を取り合いながら楽しみに待ちましょう。
この記事でご紹介した、我が家の喘息持ちの息子とのリアルな寝かしつけ体験談が全国のパパさんたちにとって、少しでも具体的なヒントとなり穏やかな夜を取り戻すための一助となることを、同じ子育てに奮闘する一人のパパとして、心の底から願っています。